- ホーム
- 南知多町 『時間の森』 ~建物で旅する愛知
南知多町 『時間の森』 ~建物で旅する愛知
愛知県知多郡南知多町と言えば・・・
海の幸がおいしい・夏はビーチにパラソルがびっしり並ぶ、砂粒が細かく美しい海水浴場・タコ、フグが有名な日間賀島、篠島・観光できる施設がたくさんある町ですよね。
今回は、「心地よい空間」建築を広義に捉えて、南知多町内海にある「ガーデン」を紹介したいと思います。
 時間の森(ときのもり)
時間の森(ときのもり)
海岸沿いに走る247号線から小路に入り、ずんずん山道を登っていきます。「本当にこの道で大丈夫??」という雰囲気ですが、ちょっと非日常の雰囲気で不安半分、冒険のような楽しみ半分。駐車場の案内が現れて、一安心しました。入口も、行く先がどうなっているのかワクワクを誘うような出で立ちです。

マイナスイオンを浴びながら先に進むと、自然の中のガーデンが迎えてくれます。


 「ステキ!!」と「維持管理が大変そう!」の感想が同時に湧きました。
「ステキ!!」と「維持管理が大変そう!」の感想が同時に湧きました。
人と自然の豊かな空間とは
こちらで「コノポノ」というキッチンカーのお店をされているユウキさんにお話を伺いました。
約16年前、こちらの山を知人に紹介してもらい、海と空、山の自然、ロケーションの素晴らしさに惹かれ、パートナーさんとともに借りることに。そして、この素晴らしい空間を独り占めしてはもったいない!という考えから、「時間の森(ときのもり)」という公園として一般の方に無料開放して楽しんでもらえるよう、8年かけてジャングルのような状態から開拓をされました。(すごい!) この環境でコーヒーを飲んでもらえたら・・・と、一般開放した1年後からキッチンカーを始めたそうです。

ガーデンは、ユウキさんの花好きの趣味が高じて独学で作っていったとのこと。ターシャ・テューダーさんのような、作りこみすぎないナチュラルな雰囲気のお庭は、一般のご家庭でも参考にしていただけるところがたくさんあるのではないかと個人的に感じています。
自然農法にこだわって、自然に種がこぼれたものや、近所のミカン畑から遊びに来たミツバチに助けてもらいながら、次の年に芽が出て花が咲くのを楽しむ、毎年少しづつ少しづつ、自然のままを壊さない、自然の力でアップデートしていくのを見守っているような姿勢がとてもすてきだと思います。
5年ほど前には、こちらで結婚式を挙げた方もいらっしゃったそうです。
また、時々他の飲食のキッチンカーがコラボしてお店を出すこともあるそうです。
時間がゆっくり感じるベンチ
パートナーさんが作ったデッキや机ベンチも、「ここに座ってのんびりしたら気持ちいいね」という場所を選びながら、ご自分で設置していったそうです。自然の中に溶け込んで雰囲気にマッチしていて、どのベンチも「ちょっと座ってみようかな?」と思わせる造りになっています。
身体と心にいいもの
キッチンカー「coffee & juice stand Kono pono(コノポノ)」のメニューは、「身体にいいものを」とのことで、自然由来の物を使った飲み物、食べ物を提供しています。梅酵素(自家製)ジュースやカッサータをいただきましたが、とてもおいしかったです。

 広い敷地で、モグラや雑草、落ち葉と共存しながら、心地よい空間を維持するのは、やはり大変とのことですが、それでも「自然の生命力に魅了されてしまっている」と、これからの展望をニコニコお話ししてくださるユウキさんは楽しそうで、とてもすてきな方でした。
広い敷地で、モグラや雑草、落ち葉と共存しながら、心地よい空間を維持するのは、やはり大変とのことですが、それでも「自然の生命力に魅了されてしまっている」と、これからの展望をニコニコお話ししてくださるユウキさんは楽しそうで、とてもすてきな方でした。
空 海 豊かな緑
奥に進むと、海を臨めるベンチで飲食したり、のんびり過ごすこともできます。



南知多町にお立ち寄りの際は、追われる日常から一時ほっと過ごせる公園「時間の森」で、「コノポノ」のおいしい飲み物や食べ物を楽しんでみてはいかがでしょうか? 自然に触れてリフレッシュできますよ。
情報は下記よりご確認ください
【時間の森 南知多 Instagram】 @tokinomori_morin
【コノポノ Instagram】 @coffeestand_kono.pono
【時間の森 X】 @tokinomori22
愛知県知多市といえば・・・
工業・農業・木綿・海水浴のできる海 と、たくさんの観光・産業がありますが、今回は、「梅」で有名な佐布里地区にある『佐布里緑と花のふれあい公園』と、公園内に4月17日リニューアルオープンした『KonoMachi Cafe(コノマチ カフェ)』をご紹介します。

ここでクイズです!
佐布里緑と花のふれあい公園の周辺には何種の梅の木が植わっているでしょうか?
→ 答えは後ほど…

明治時代後期、一本の木から多くの実が収穫でき現金収入も多い佐布里梅が競って植えられ、やがて梅林になっていったそうです。
平成13年に佐布里緑と花のふれあい公園が開園され、佐布里池・公園周辺には愛知県内一を誇る約6,000本(令和2年4月現在)の梅林が広がり親しまれています。毎年2月中旬から3月中旬に、「佐布里池梅まつり」が開催されます。
佐布里緑と花のふれあい公園は、広々とした気持ちの良い広場の中に、お子様の遊び場、鑑賞温室、バーベキューハウス、地元の土産品を扱う売店、展示ホール、佐布里の歴史と文化を伝える情報展示室、梅を使った料理教室や園内の素材を使ったクラフト講座を受けられる体験工房など、梅の開花時期だけでなく、通年楽しくゆっくり過ごせる公園です。
知多市と知多メディアスネットワーク(株)のネーミングライツ契約締結に伴い、公園内にあるKonoMachi Cafeは、4月にリニューアルオープンしました。この度改装工事に携わらせていただきましたので、内装のコンセプトや想いについて記していきたいと思います。
① 和から和モダンへ 幅広い年齢層のお客様の憩いの場所を目指して
今までの重厚感あるしっかりした造りを残しつつ、新しいモーニング・ランチメニューの雰囲気にもマッチした、幅広い年齢層のお客様が集える空間をとのことで内装を計画させていただきました。
 |
 |
② テーマは梅
特に目が行くのは、緑と花をイメージした配色かと思います。公園のテーマ・コンセプトを表現できるように、カウンターの上と、ソファの配色を工夫しました。

店内が広いので、存在感のある雰囲気の良い照明で、空間を引き締めています。
お会計後のセルフサービスの動線をスムーズにするためのカウンター配置も工夫しました。
③ 公園の景観との調和 居心地の良い空間づくり
今までは椅子とテーブル席のみでしたが、ソファ席でくつろげるようになりました。

また、せっかくきれいに整備された広い公園の景色を、ゆったり飲食しながら愛でられないのはもったいない!ということで、窓側に外の景色を臨めるカウンター席を設けました。
私がモーニングに伺った日はとてもお天気も良く、広場でたくさんの小学生くらいのお子様が輪投げやボールを使った外でできるゲームを楽しむイベントが行われていました。カウンター席から、お子さんたちが元気に遊ぶ姿を見ながら、おいしいコーヒーやパンをいただく時間は至福のひと時でした。

個室スペースもあります。車いすで来店したご高齢のお客様が、ゆったりとお茶を飲んでいらっしゃいました。
格子で仕切ることで、閉塞感なく少し籠った落ち着く空間になっています。

フードコート形式なので、食事の購入後は店内の席はもちろん、軒下のテラス席や、公園内の芝生の上・ベンチでも外の空気を吸いながらピクニック気分で過ごすこともできます。
その日の気分や過ごし方に合わせて選んでみてはいかがでしょうか?

先日伺った際、公園内ではBBQをお仲間や家族で楽しむ方も多くいらっしゃいました。
梅の花の時期はもちろん、梅以外の花もきれいに手入れされているのでのんびりお散歩したり、講座では日常の中ではなかなか出来ない体験をしたり、様々な楽しみ方があります。
KonoMachi Cafeは、おいしい飲み物とごはん、とても丁寧に接してくれるスタッフの方が印象的でした。
皆さんも、知多市に行った際は、公園やカフェに立ち寄ってみてくださいね。
(詳細情報、お問合せについては佐布里緑と花のふれあい公園HPをご覧ください)
クイズの答え 佐布里梅を始め、青軸や白加賀など25種の梅が植樹されています。
 |
 |
| before | after |
「2030年にはZEH水準の省エネ住宅が新築の基準に」
皆さん、「ZEH水準」という言葉を聞いたことありますよね。なんとなく「省エネ住宅の基準」というイメージはありますが、具体的にはどういうこと?を今回はお話していきます。
地球温暖化は深刻な問題となっており、気温の上昇を抑えるには温室効果ガスの排出量削減が不可欠です。気温の上昇が続くと、異常気象による干ばつや洪水などの発生が懸念され、人間や動植物の存続の危機にもつながる可能性があります。政府は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた取り組みの一環として、2030年には新築住宅の省エネ基準をZEH水準に引き上げる方針を掲げています。
2025年4月、すべての新築住宅に「省エネ基準適合」が義務化になりました。
住まいの熱を快適にコントロールできる、高断熱・高気密に作られたエネルギー消費量を抑える性能を備えた住宅は、ランニングコストを抑え、健康で快適に過ごせるメリットがあります。優遇制度も充実しています。
「省エネ住宅 『ZEH』『ZEH水準』の違い」
ZEH (ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)は、再生可能エネルギー(太陽光発電・風力発電機など)を活用して、一次エネルギー消費量(冷暖房・換気・急騰・照明などのエネルギー合計)の収支を概ねゼロ以下にする住宅です。
ZEH水準は、断熱材や窓、エアコンや給湯器などの高効率な設備システムを活用して省エネ性能を高めた基準です。太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入が必須ではないので、ZEHよりも初期費用を抑えながら光熱費削減が可能です。
『ZEH水準住宅について』
住宅性能表示基準における「断熱等性能等級5」および「一次エネルギー消費量等級6」を同時に満たしていることが条件です。
暖冷房、換気、給湯、照明など住宅で使うエネルギー消費量に関する基準があります。(一次エネルギー消費量基準)
高断熱高気密で、快適な住環境を実現します。
『ZEH水準のメリット』
1. 光熱費の負担が軽くなる
断熱性能の強化 高効率設備の導入 で、使用するエネルギーを大幅に減らすことができます。同時に、日々の光熱費が削減できるので、長期的にみるとランニングコストが削減できます。
2. 優遇制度
住宅ローン減税やフラット35借入金利の引き下げなどの優遇を受けることができます。
・住宅ローン減税とは、ローンを借りて住宅を取得すると、年末のローン残高の0.7%相当額が所得税・住民税から一定期間控除される制度です。
年間の合計所得2,000万円以下の場合に利用できます。対象物件は床面積や築年数で一部制限があります。ローン残高の限度額は住居の省エネ性能や入居年などによって異なります。
・【フラット35】とは、「全期間固定金利」で返済することができる住宅ローンです。省エネルギー性能の優れた住宅を取得する場合、一定期間金利が引き下げられるフラット35Sが利用できます。
『補助金との関係』
例:戸建住宅(注文・建売)において、ZEH※の交付要件を満たす住宅を新築する者に対する定額補助:40万円/戸
要件によって補助金交付があります。
※「ZEH」は、快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化(断熱等性能等級5に相当。)と高効率設備によりで きる限りの省エネルギー(一次エネルギー消費量等級6に相当。)に努め、太陽光発電等によりエネルギーを創るこ とで、1年間で消費する住宅のエネルギー量が正味(ネット)で概ねゼロ以下となる住宅。
『GX志向型住宅と補助金について』
GX志向型住宅とは、ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する脱炭素志向型の住宅です。・断熱等性能等級 ・再生エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率 ・再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量削減率 ・高度エネルギーマネジメントの導入 の要件を満たした住宅※が、補助金の対象となります。※補助対象住宅の要件により補助額も様々です。例:GX志向型住宅 1戸あたりの補助額160万円 長期優良住宅 1戸あたりの補助額80万円
「性能の考え方」
「性能」は、備えれば備えるほど安心感があるかもしれませんが、過剰に備えすぎて「予算に合わない」「暮らしに合わない」とならないように計画したいですよね。立地や間取りと合わせて、省エネ性能もあなたにあった住宅を見つけてください。詳しくはオワリヤまでご相談ください。
皆様、赤レンガ建物が愛知県半田市にあるのをご存じですか?
今回は「半田赤レンガ建物」を紹介します。

ここでクイズです!
問1. 日本の赤レンガ建物の中で、一番レンガの数が多く使用されている建物は?
問2. 日本の赤レンガ建物の中で、半田赤レンガ建物はレンガが使用されている数が何番目に多いでしょう?
→ 答えは後ほど…
半田赤レンガ建物には3つの意義があります。
1. 明治時代にビール工場として誕生 郷土産業の遺産
2. 大規模なレンガ造り建築の遺構 建築物としての遺産
3. 建物に残された機銃掃射痕 戦争の遺跡
丸三ビール・カブトビールの歴史もとても興味深いお話ですが、今回は建築の視点から半田赤レンガ建物を見ていきたいと思います。
① 地元の起業家の出資 豊富な財力と時代の最先端の技術を導入した建物
明治20年(1887年)日本酒に重い税が課せられるようになり、ビールに着目した中埜又左衛門(中埜酢店(ミツカン)4代目)、盛田善平(敷島製パン創業者)らによって、醸造の町半田でビール製造が始まります。順調に売り上げを伸ばし、生産能力向上のため、地元の醸造家たちの出資により、1898年(明治31年)半田町榎下(現 愛知県半田市榎下町)に新ビール工場となる半田赤レンガ建物が創設されました。当時の工場敷地総面積は約1万坪。現在隣接しているナゴヤハウジングセンターの敷地も、当時はビール工場だったそうです。当時の建物は取り壊された部分もあり、現在はその一部が当時の外観を損なわないように耐震補強や改修を施して残されています。
とても大規模な工場だったんですね。常設展示室には、揃いの法被で作業をしている昭和初期の様子を伝えるジオラマが展示してあります。また、外壁東側には、当時の建物(4階建ての東棟)が伸びていた屋根跡を見ることができます。

② 明治時代を代表する建築家 妻木頼黄の設計
半田赤レンガ建物の実施設計をした妻木頼黄(つまきよりなか)は、・東京日本橋の意匠設計(デザイン)・横浜税関新港埠頭倉庫(現 横浜赤レンガ倉庫)・横浜正金銀行本店(現 神奈川県立歴史博物館)などを設計した人物です。
③ レンガの積み方とハーフティンバー構造
日本の赤レンガ建物で多く使われたレンガの積み方には「イギリス積み」と「フランス積み」があります。半田赤レンガ建物は、レンガを長手面だけの段、小口面だけの段を1段おきに積む方式の「イギリス積み」を採用しています。〔特徴〕・強度が強い・土木建造物や鉄道の橋梁などによくみられる
レンガには漢数字やカタカナが彫られているものがあり、現在でいうロット番号の役割を果たしていました。
半田赤レンガ建物に使用されている多くのレンガが、愛知県安城市のレンガ製造所のものだそうです。現在のように便利な重機もなかったと思いますが、製造・運搬・施工も大変な作業だったのだろうと想像します。
半田赤レンガ建物の南側(大通り沿いから見える建物)には、木材の柱とその間をレンガで埋めた部分があります。これをハーフティンバー構造と言い、世界遺産の富岡製糸場などで見られる珍しい建築様式です。木造骨組みの間に、土、石、泥土をつなぎにしたレンガを埋め込んで強度を持つ壁を造り上げていて、装飾的な効果もあります。

④ 断熱の工夫
ビール工場として、熟成や貯蔵のために温度を0度にする必要がありました。設計者 妻木頼黄は、貯蔵室部分の建物自体を冷蔵庫にするため徹底的な断熱の仕組みを施しました。
天井が2重3重に交互にアーチ状になっており、間に空気層を作っています。一番上にはコンクリートを流し入れ、その上におがくずやもみ殻を敷き詰めて更に断熱し、カブトビールの適温を保つ工夫をしていました。
壁の厚さが1.5mの部分もあります。2重から5重の空気層を有する複壁という壁も断熱の工夫で、気温が変化しても室温を一定に保つことができます。壁の断面が見られるような展示もあります。
現在の住宅も、快適に過ごすための様々な断熱材がありますが、明治時代でも目的に合わせた断熱の工夫がされていたのだと感じました。
また、2階3階にも工場が繋がっているため、耐火床という構造で、万が一火事が起きても貯蔵しているビールに引火しないような対策がなされています。

⑤ ビール樽の貯蔵跡を見る 収納の工夫
ビール樽1樽当たり、約6000ℓ(瓶にすると約9500本分)が入るものが上下に積み重ねられ、貯蔵庫に保管されていました。貯蔵庫だった部屋は、ぴったりと樽が収まるように少し円形に壁が削られています。そんな部分も是非建物内で見ていただき、当時を感じていただけたらと思います。

⑥ 歴史を今に繋ぐ耐震工事 明治を感じる柱頭
建物を保存をしていくことが決定してから、老朽化や改修による構造体の欠如など、耐震上の不安がありました。このため、レンガ壁に鉄筋挿入の工事や、床補強のため鉄筋コンクリートの工事を行い、現在は安心して見学、使用できる施設となっています。
実際に東棟で使用されていた柱頭(ちゅうとう)が、屋外に展示してあります。この柱頭は、鉄の柱の上に設置され梁を支えていたものです。頑丈で火に強い建物とするために、柱や梁には鉄が使われていたようです。重厚感があります。

私は半田市民ですがイベントに参加するなどの機会でしか赤レンガ建物に行ったことがありませんでした。初めてじっくり見学して、約130年の歴史を感じながら、近くに住んでいるのに知らなかった文化財のことを楽しく学びました。
皆さんも、ぜひ半田市にいらっしゃった際には、半田赤レンガ建物の歴史を感じていただけたらと思います。(料金など詳細は、半田赤レンガ建物のHP等を参考になさってください。)
クイズの答え 問1. 日本の赤レンガ建物の中で一番レンガ使用数が多いのは「東京駅」 問2. 半田赤レンガ建物は、日本の赤レンガ建物の中で「4番目」にレンガ使用数が多い。東京駅、横浜新港埠頭倉庫、北海道庁、に次ぐ大規模な建築物です。
家づくりを検討していく過程で、完成見学会やモデルハウスを見学してご自分の家の参考にする方は多いと思います。
今回は、完成見学会の家(実邸)とモデルハウスの違い、完成見学会に参加するメリットなどを詳しくご紹介します。楽しく理想の家づくりを進める中で参考にしていただけたら嬉しいです。

目次
| 1.完成見学会とモデルハウスはどう違うの? |
| 2.実際の生活空間を体感できる |
| 3.家づくりのストーリーを聞いて体感できる |
| 4.細部の仕上がりを確認できる |
| 5.住人の声を聞くことができる |
| 6.開催予定の住宅の紹介 |
1. 完成見学会とモデルハウスはどう違うの?
実際の生活において、個々のライフスタイルや家族構成に応じたカスタマイズが必要です。完成見学会では、そうした個別のニーズに応じた住宅の実例を見ることができ、自分の理想の住まいを具体的にイメージする手助けとなります。モデルハウスでは見えない、等身大の実生活に即した工夫や、住みやすさを追求した設計を確認することができます。
2.実際の生活空間を体感できる
住宅完成見学会では、実際に人が住むことを前提に設計された家を見学することができます。実際の生活感や居住者のニーズに応じた工夫が施されている実邸を見ることで、より現実的なイメージを持つことができます。

上の写真のお住まいでは、
「ランドリールームを廊下を介してすぐの中庭に配置して、家事動線をスムーズにしたい」
「中庭からの採光を感じながら、リビングでゆったり過ごしたい」
など、お客様の「こんな暮らしがしたい!」が詰まっていて、お客様と私たちのやりとりから形になっています。
そんな実際の生活空間を、ご自分のしたい暮らしのイメージを膨らませていただきながら見学してもらいたいと思います。
3.家づくりのストーリーを聞いて体感できる
家づくりには多くの段階があります。例えば、住宅会社を選ぶ、土地を探して決定する、住宅ローンを選ぶ、お打合せを重ねてプラン・仕様を決定する…
一つ一つの段階で、それぞれの居住者のストーリーがあり家が完成します。
建物を見るだけでなく、その家を建てる過程の話やどんな暮らしをしていきたいかを聞いてご自分の家づくりにフィードバックしていただき、実際の家を見ることで形になったものを体感することができます。
4. 細部の仕上がりを確認できる
建築部材には様々な種類があり、生活や環境に合わせた選定をお客様とじっくりお打合せですり合わせながら決定していきます。見学会では、例えば壁紙の質感や床材の触り心地、照明の配置など、カタログや写真ではわからない細部の仕上がりや素材の質感、施工の仕上がりや職人の技術を、直接確認することができます。また、なぜその材料を使用したのかや性能についてその場で話を聞くこともできます。

5. 住人の声を聞くことができる
見学会によっては、実際に住んでいる方の声を聞くことができる場合もあります。住み心地や、住んでみて初めてわかった利点や改善点など、リアルな体験談を聞くことができるのは大きなメリットです。
6.開催予定の住宅の紹介
住宅完成見学会は、地域や住宅メーカーによって定期的に開催されています。参加を希望される方は、各メーカーのウェブサイトや広告をチェックすることで、最新の情報を得ることができます。また、事前に予約が必要な場合もありますので、早めの計画をお勧めします。
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございます。
住宅完成見学会を有意義な機会にしていただき、理想の住まいを見つける一助としてください。
当社でも随時見学会を行っております。ご来場いただけましたら幸いです。
お気軽にご参加ください。
注文住宅を建てるとき、多くの方が内装デザインの決め方に悩まれています。内装は毎日の暮らしに大きな影響を与えるため、慎重に選びたいものです。この記事では、注文住宅の内装デザインを失敗しないためのポイントについて解説します。
注文住宅の内装デザインで失敗しないためのポイント

注文住宅の内装選びは、完成してから後悔したくないものです。内装は家族全員の毎日の生活に関わる大切な要素であり、建材の選択から色の組み合わせまで、さまざまな決断が必要になります。ここでは、失敗しない内装選びのための基本的なポイントを紹介します。
好みのテイストを見極める
内装デザインを決める前には、まず自分の好みのテイストを見極めることが重要です。ハウスメーカーのウェブサイトや住宅雑誌・SNSなどで多くの実例写真を見ることをおすすめします。モダン・ナチュラル・和風・アメリカンなど、さまざまなテイストがありますが、最初から絞り込まず幅広く見ることが大切です。気に入った写真は保存しておき、デザインを検討するときの参考にするとよいでしょう。
実際に展示場やモデルハウスに足を運び、実物の空間の雰囲気を体感することも効果的です。好みのテイストが分かれば、その後の内装材の選択もスムーズになります。
家族で方向性を共有する
内装デザインは、家族全員で方向性を共有することが大切です。特にリビングやダイニングキッチンなど、家族が集まる共有スペースは、全員の意見を取り入れて決めていく必要があります。家族それぞれの好みや生活スタイルを話し合い、全員が心地よく過ごせる空間を目指しましょう。
寝室や子供部屋など、個人で使用する部屋については、主に使う人の意見を重視して決めることもできます。方向性が定まらないまま内装を決めると、時間がかかってしまうだけでなく、後々の不満にもつながる可能性があります。
実物サンプルでイメージを確認する
内装材を選ぶときは、必ず実物のサンプルで確認しましょう。カタログやウェブサイトの写真だけでは、実際の色味や質感を正確に把握することは難しいものです。壁紙や床材のカットサンプルを手に取り、実際の照明環境で見てみることで、より正確なイメージをつかむことができます。
また、同じ素材でも照明の種類や自然光の当たり方によって見え方が大きく変わることがあります。実際の生活シーンを想定しながら、朝・昼・夜など時間帯による見え方の違いも確認するとよいです。
内装のスタイル別特徴と魅力

内装のスタイルには様々な種類があり、どのスタイルを選ぶかは家族の好みや生活スタイルによって変わってきます。それぞれのスタイルの特徴を理解することが、理想の住まいづくりの第一歩となります。
モダン・スタイリッシュな内装
モダン・スタイリッシュな内装は、シンプルでありながら洗練された空間を演出します。白や黒・グレーを基調とした配色が特徴で、直線的なデザインと組み合わせることで都会的な印象を作り出します。床材には光沢のあるフローリングやタイルを使用し、建具も同様にシンプルなデザインを選ぶことが一般的です。
照明は、シーリングライトやダウンライトなど、すっきりとしたものを採用します。家具も直線的なデザインのものを選ぶことで、統一感のある空間になります。このスタイルは、掃除がしやすく、メンテナンスもしやすいのが特徴です。
自然素材を活かしたナチュラルな内装
自然素材を活かしたナチュラルな内装は、木の温もりを感じられる落ち着いた空間を作り出します。床材には無垢材や、つや消しの木目調フローリングを使用し、壁紙も木目調や淡い色味のものを選ぶとよいでしょう。
建具も木目を活かしたデザインにすることで、統一感が生まれます。照明は、温かみのある電球色を基調とし、ペンダントライトや間接照明を組み合わせることで、やわらかな雰囲気を演出できます。このスタイルは、長く住んでも飽きが来にくいのが特徴です。
ホテルライクな高級感ある内装
ホテルライクな内装は、上質で洗練された空間を目指すスタイルです。床材には大判のタイルや高級感のあるフローリングを採用し、壁紙も光沢のある素材や、テクスチャーの美しいものを選びましょう。
建具は重厚感のあるデザインとし、天井までの高さにすることで開放感を演出します。照明はシャンデリアや上質なペンダントライトを取り入れ、間接照明と組み合わせることで、品のある空間になります。
内装の決め方と具体的な進め方
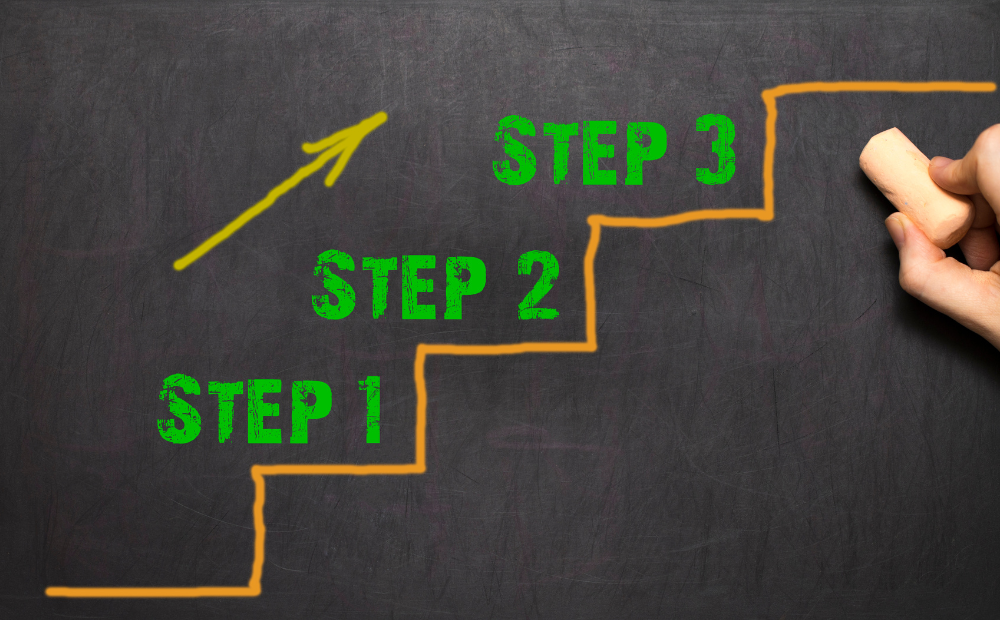
内装を決める際は、順序立てて進めることが重要です。床・壁・天井といった基本的な要素から、照明や収納までバランスの取れた空間づくりを目指します。ここでは、内装を決める際の具体的な手順を解説します。
床材選びのポイント
床材は、内装全体の印象を大きく左右する重要な要素です。主にフローリングとタイルから選ぶことになりますが、それぞれに特徴があります。フローリングは温かみがあり、歩きやすく、メンテナンスも比較的簡単です。
一方、タイルは掃除がしやすく、傷つきにくいという特徴があるため、水回りに適しています。床材を選ぶ際は、部屋の用途や家族の生活スタイルを考慮することが大切です。子育て中の家庭では傷がつきにくい素材、ペットがいる家庭では掃除のしやすい素材を選ぶとよいでしょう。
壁紙とクロスの選び方
壁紙は部屋の雰囲気を決める大切な要素です。一般的なビニールクロスから、高級な輸入壁紙まで、様々な種類があります。選ぶ際は色や柄だけでなく、機能性も重要なポイントとなります。汚れに強い防汚性・キズに強い耐久性・消臭効果のある機能性など、用途に応じて選択が大切です。
壁紙は実際の空間に貼った時と、サンプルで見た時では印象が大きく異なることがあります。これは面積効果と呼ばれる現象で、広い面積になると色の見え方が変化するのが特徴です。そのため、なるべく大きなサンプルを活用し、確認するのがいいでしょう。
建具やドアの選定基準
建具は、デザイン性と機能性の両方を考慮して選びます。デザインは内装全体の雰囲気に合わせることが基本です。モダンな空間には直線的でシンプルな建具、ナチュラルな空間には木目を活かした建具が調和します。
機能面では、開閉方式や防音性・断熱性なども重要な選定基準となります。また、建具の色は空間全体のカラーバランスを考えて選びましょう。
注文住宅の内装をおしゃれに見せるコツ

内装をおしゃれに見せるには、いくつかの重要なポイントがあります。色使いや光の取り入れ方・アクセントの付け方といった基本的な要素を押さえることで、より魅力的な空間を作れます。
カラーバランスのとり方
内装の色使いは、全体の印象を大きく左右する重要な要素です。基本的には3色以内でまとめることがよいといわれています。床・壁・天井などの大きな面積を占める部分をベースカラーとし、建具や家具などをメインカラー、小物類をアクセントカラーとして扱います。
ベースカラーは面積が大きいため、落ち着いた色味を選ぶことが一般的です。白やベージュなどの明るい色を使うと、空間が広く感じられます。メインカラーはベースカラーと調和する色を選び、アクセントカラーは空間のポイントとして効果的に使います。全体のバランスを考えながら、色の組み合わせを決めていきましょう。
光と影を意識した設計
光の取り入れ方は、内装の印象を大きく変える重要な要素です。窓の配置や大きさ・向きによって、自然光の入り方が変わってきます。南向きの窓からは明るい光が入りますが、西日が強く入る場合は室温が上がりやすいという特徴があります。
照明計画では、全体照明・作業照明・雰囲気照明を組み合わせることが大切です。天井照明だけでなく、スポットライトや間接照明を効果的に使うことで、空間に奥行きや立体感が生まれます。光の明るさや色味も、空間の雰囲気に大きく影響します。
アクセントウォールの効果的な使い方
アクセントウォールは、空間に変化をつける効果的な手法です。壁の一面だけ異なる素材や色を使うことで、空間にメリハリが生まれます。素材には、アクセントクロス・タイル・木材・エコカラットといった様々な選択肢があります。
アクセントウォールを設ける位置は、家具の配置や動線を考慮しましょう。リビングでは、テレビ台やソファの背面の壁に設けることが多く、玄関やダイニングでも効果的です。
まとめ
注文住宅の内装デザインは、住まいの印象を大きく左右する重要な要素です。好みのテイストを見極め、家族で方向性を共有し、実物サンプルでイメージを確認することが失敗しないポイントとなります。内装のスタイルは、モダン(スタイリッシュ)・ナチュラル・ホテルライクなど様々な選択肢があり、それぞれの特徴を理解することが大切です。
床材、壁紙、建具などの選定では、デザイン性と機能性の両方を考慮し、カラーバランスや光の取り入れ方にも注意を払う必要があります。内装選びで迷ったら、株式会社デザインセンターオワリヤにご相談ください。店舗設計で培った技術と経験を活かし、お客様の理想の住まいづくりをサポートいたします。
注文住宅の建築を考えるとき、適切な広さと予算の検討は大切です。その中でも30坪は、3〜4人家族が快適に暮らせる人気の広さです。この記事では、30坪の注文住宅の相場・間取り・費用計画について解説します。
30坪の注文住宅はこんな家族におすすめ

家づくりで最初に考えるのは、家族それぞれが心地よく過ごせる広さです。30坪の注文住宅は、ライフステージの変化にも対応できる住まいとして支持されています。
理想的な家族構成
30坪の注文住宅は、3〜4人家族に適した広さです。一般的に1人あたり8坪が必要といわれており、30坪であれば夫婦と子ども2人の4人家族でも十分な広さを確保できます。寝室やリビング・子ども部屋などの必要な空間をバランスよく配置することができ、家族の成長に合わせて部屋の使い方を変えることも可能です。共働き家庭では在宅ワークスペースの確保も考慮でき、現代のライフスタイルに柔軟に対応できる広さとなっています。
快適に暮らせる広さのめやす
30坪の住まいでは、リビングダイニングを中心に、各個室をゆとりある広さで設計することができます。一般的な4人家族の場合、リビングダイニングは15〜16畳、主寝室は8畳、子ども部屋は6畳程度を確保可能です。玄関から各部屋へのアクセスもスムーズで、日々の生活のしやすさを重視した間取りを実現できる広さです。
30坪のメリット・デメリット
30坪の住まいの大きな魅力は、必要な部屋数を確保しながらも、適度なゆとりを持った空間づくりができる点です。リビングには来客用のスペースも設けられ、子どもの成長に応じて個室を分けることもできます。
また、建築費用の面でも35坪以上の住宅と比べて土地代や建築費を抑えられる利点があります。ただし、大きな収納スペースや趣味の部屋など、特別な用途の部屋を多く設ける場合は工夫が必要です。家族構成や暮らし方によって、収納計画や間取りの工夫が求められます。
30坪注文住宅の費用はいくら?

家づくりを始める前に、必要な予算を把握しておくことが大切です。地域や建築会社によって費用は異なりますが、平均的な相場を知ることは計画の第一歩となります。
全国平均の建築費用
住宅金融支援機構の調査によると、30坪の注文住宅の全国平均建築費用は約3,000万円です。この金額には、本体工事費と諸経費が含まれています。本体工事費は建物を建てる基本的な費用で、全体の約70%を占める計算です。
諸経費には、設計費用や申請費用・税金などが含まれており、全体の約10%に相当します。一方、残りの20%は外構工事や設備工事などの付帯工事費用が占めています。建築費用の相場を知ることは、予算計画の基準として重要です。
参考:住宅金融支援機構|フラット35利用者調査(2022年度)
地域別の価格差
住宅金融支援機構の調査によると、注文住宅の建築費用には地域差があります。これらの違いは、地域ごとの人件費や材料費の違いによるものです。建築を予定している地域の相場を確認することは、より現実的な予算計画につながります。
| エリア | 坪単価 | 30坪の場合 |
| 三大都市 | 105万円 | 3,151万円 |
| 首都圏 | 107万円 | 3,227万円 |
| 近畿圏 | 104万円 | 3,138万円 |
| 東海圏 | 100万円 | 3,000万円 |
参考:住宅金融支援機構|フラット35利用者調査(2022年度)
必要な諸経費
建築費用以外にも、住宅を建てるためには様々な諸経費が必要です。具体的には、建築確認申請費用・地盤調査費用・登記費用などが含まれます。また、外構工事費用も重要な支出です。
庭やカーポート・フェンスなどの外構工事は、建物の完成後の暮らしやすさに大きく影響します。家づくりの予算を考える際は、これらの諸経費についても計画的に準備を進めることが大切です。
30坪注文住宅の資金計画

注文住宅を建てる際は、長期的な視点での資金計画が重要です。住宅ローンの返済や、将来的な修繕費用なども考慮に入れた計画を立てることが大切です。
年収別の住宅ローン目安
住宅ローンを検討する際は、建築費用に加えて、諸経費や外構工事などの費用も考慮する必要があります。借入可能額は、年収や他の借入金の有無、勤務年数などの条件によって変動します。住宅ローンの詳しい条件は、金融機関に相談することがおすすめです。
月々の返済プラン
住宅ローンの返済プランは、借入額と返済期間・金利によって決まります。返済期間は35年以内が一般的で、月々の返済額は年収の25%以内に収めることが推奨されています。このほかに、固定資産税や火災保険料、光熱費などのランニングコストも考慮しなければいけません。
また、将来的な収入の変動や教育費などの支出も見据えて、余裕を持った返済計画を立てることが重要です。特定の金融機関に限定せず、複数の金融機関で返済プランを比較検討することをおすすめします。
30坪注文住宅の人気の間取り

30坪という広さを最大限に活かすためには、家族の生活スタイルに合わせた間取りの工夫が重要です。現代の暮らしに適した間取りの特徴をご紹介します。
2階建て4LDKの特徴
30坪の注文住宅では、2階建て4LDKが最も人気のある間取りプランです。1階には、約20帖のLDKを中心に、和室や水回りを配置します。玄関からリビングまでの動線や、キッチンから水回りへの家事動線も重要なポイントです。
2階には主寝室と子ども部屋を配置し、家族のプライベート空間を確保します。階段下や廊下部分には収納スペースを設けることが可能です。各部屋の配置は、採光や通風・家族の生活リズムを考慮して決めていきます。
平屋3LDKの魅力
平屋の3LDKは、シニア世代や小さな子どもがいる家族に人気のプランです。階段の上り下りがないため、将来的なバリアフリーにも対応できます。30坪の平屋では、広々としたLDKを中心に2つの個室と水回りをコンパクトに配置します。天井高を活かした開放感のある空間づくりが可能です。
また、庭やウッドデッキなどの外部空間との繋がりも重要なポイントとなります。周囲からの視線を気にせず、光と風を取り入れる工夫も平屋ならではの特徴です。
効率的な収納計画
30坪の住まいでは、限られた空間を有効活用するための収納計画が重要です。玄関には、コート類や靴、傘などを収納できるシューズクロークを設置します。リビングには、掃除用具や季節の家電などを収納できる物入れを確保します。
2階建ての場合、階段下を収納スペースとして活用することも可能です。寝室には大容量のウォークインクローゼットを設け、衣類や寝具類をまとめて収納できます。水回りには、洗剤や掃除用具などの収納スペースを確保し、使いやすい家事動線を実現します。
30坪の注文住宅で費用を抑えるポイント
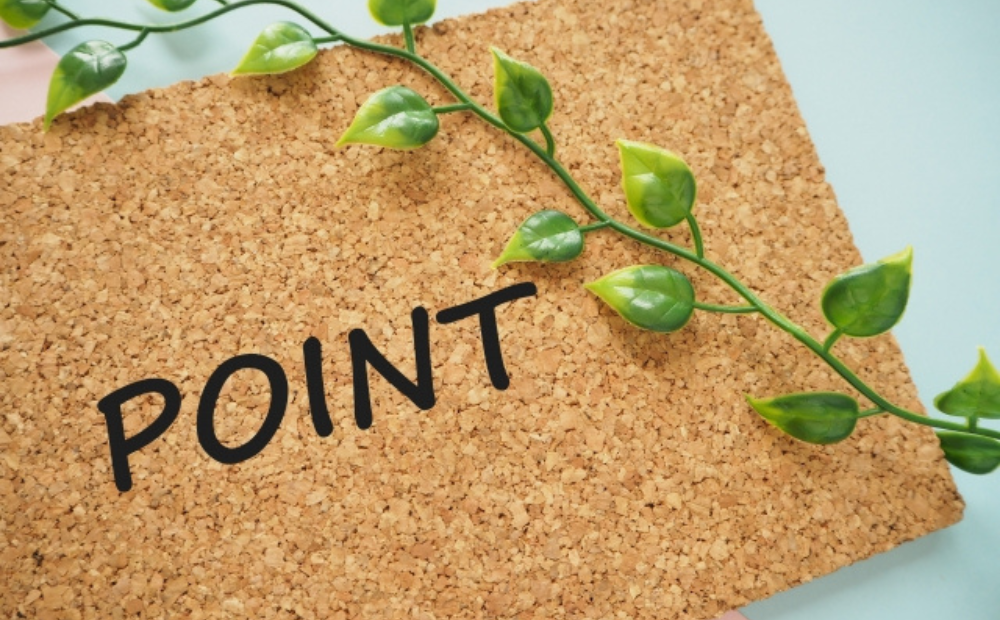
建築費用を抑えながら、快適な住まいを実現するためのポイントをご紹介します。デザインや構造の工夫で、予算内での理想の家づくりが可能となります。
シンプルな外観デザイン
建築費用を抑えるためには、外観デザインをシンプルにすることが重要です。凹凸の多い外壁や複雑な屋根形状は、資材費と工事費用を押し上げる要因となります。真四角に近い建物の形状であれば、外壁の施工面積が最小限となり、屋根の工事費用も抑えられるでしょう。外壁材は、メンテナンス性の高いサイディングを選ぶことで、長期的なコストダウンにもつながります。
総2階建ての特長
総2階建ての住宅は、30坪の土地を最大限に活用できる構造です。1階と2階の床面積がほぼ同じ大きさになるため、基礎や屋根の面積が小さくなり、建築コストを抑えられます。断熱性能も高くなりやすく、省エネルギー性能の面でもメリットがあります。
水回りの配置のコツ
水回りの設備は建築費用の中でも大きな割合を占めます。キッチン・浴室・洗面所・トイレなどの水回りを近くに配置することで、給排水工事の費用を抑えられます。配管の長さが短くなると、工事費用が削減できるだけでなく、メンテナンスも簡単です。2階建ての場合は、1階と2階の水回りを縦に配置することで、配管工事を効率的に行うことができます。
まとめ
30坪の注文住宅は3〜4人家族に適した広さで、建築費用の全国平均は3,000万円です。地域によって価格差があり、首都圏では3,227万円、近畿圏では3,138万円が目安となっています。間取りは2階建て4LDKが人気で、外観デザインをシンプルにしたり、総2階建てを採用することで、費用を抑えられます。
株式会社デザインセンターオワリヤは、1926年の創業以来、店舗建築で培った高いデザイン性と確かな技術力を活かし、理想の住まいづくりをサポートしてきました。豊富な経験を持つスタッフが、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた30坪の注文住宅プランをご提案いたします。家づくりのご相談は、ぜひデザインセンターオワリヤにお任せください。

注文住宅を建てようと考えた時、多くの方が気になるのが完成までの期間です。基本的な期間は8ヶ月から15ヶ月ほどかかりますが、工程や条件によって変わることがあります。この記事では、注文住宅の完成までの期間とスムーズに家づくりを進めるためのポイントについて解説します。
注文住宅の完成までにかかる期間

注文住宅は土地探しから完成まで長い時間を要しますが、それぞれの工程にかかる期間を把握しておけば、計画を立てやすくなります。ここでは、一般的な工期の目安と流れについて詳しく説明します。
全体の工期の目安
注文住宅の完成までにかかる期間は、一般的に8ヶ月から15ヶ月程度です。これは土地をすでに持っているかどうかで、大きく変わってきます。土地探しからスタートする場合は、さらに3ヶ月から半年ほどの期間が必要です。
また、プランの内容や建築工法・地域の気候なども工期に影響を与える要素となります。土地を探すところから始めると、1年から1年半ほどの期間を見込んでおくと安心です。たとえ急ぎたい場合でも、各工程に十分な時間をかけることで、家づくりの失敗を防ぐことができます。
各工程の所要期間と流れ
注文住宅の工程は、大きく分けて情報収集・プランニング・契約・建築工事の4つに分かれます。情報収集と予算の検討には1ヶ月から3ヶ月、プランニングと打ち合わせには2ヶ月から3ヶ月、契約から着工までに1ヶ月、そして建築工事には3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。工事期間中も、基礎工事・建て方工事・内装工事などの工程があるので、家づくりは余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
注文住宅の工期に影響を与える要因

注文住宅の工期は、さまざまな要因によって変動します。ここでは工期に影響を与える主な要因について説明していきます。
建築工法による違い
注文住宅の工期は、選択する建築工法によって大きく異なります。木造や鉄骨造の場合は最短で2ヶ月以上、RC造(鉄筋コンクリート造)の場合は最短で4ヶ月以上が必要です。木造住宅は比較的工期が短いものの、材料の乾燥や施工のタイミングなどで期間が変動することがあります。
鉄骨造は現場での建築期間は比較的短いものの、工場での製作期間が必要です。RC造は構造的に強固である一方、コンクリートの養生期間が必要なため、工期が長くなります。建築工法の特徴を理解し、自分の希望する家に合った工法を選ぶことが大切です。
土地の状況による違い
建築予定地の土地形状が複雑な場合や地盤が弱い場合、追加の工事が必要になるケースも考えられます。地盤調査の結果、地盤改良が必要になれば、その分だけ工期が延びるのです。敷地が狭い場合や周辺に建物が密集している場合も、工事車両の出入りや資材の搬入に制限がかかるため、作業効率が下がって工期が延びる原因となります。
季節や天候による影響
注文住宅の工事は、季節や天候の影響を大きく受けます。雨の多い梅雨時期や寒さの厳しい冬場は、工事の進行に影響が出やすい時期です。特に基礎工事やコンクリート工事は、気温や天候の影響を受けやすく、作業が中断されることもあります。
また、外壁工事や塗装工事なども天候に左右される作業です。年末年始やお盆期間は工事が休みになることが多く、これらの時期をまたぐ場合は、その分だけ工期が延びることを想定しておく必要があります。このため、着工時期の検討も重要な要素であるといえるでしょう。
注文住宅をスムーズに進めるためのポイント

家づくりを順調に進めるには、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは具体的な進め方について説明していきます。
土地探しを効率的に進める方法
土地探しを効率的に進めるには、明確な条件設定が大切です。希望するエリアや予算・土地の広さなどの条件に優先順位をつけましょう。理想の条件をすべて満たす土地を見つけるのは難しいため、譲れない条件と柔軟に対応できる条件を整理しておくと、土地選びがスムーズです。
また、土地探しの期間は3ヶ月から6ヶ月程度を目安に設定します。土地探しに時間をかけすぎると、その分だけ建築までの期間が延びてしまいます。不動産業者に相談する際も、具体的な条件を伝えることが大切です。土地の形状や向き・周辺環境なども家づくりに大きく影響する要素となります。
プランニングと打ち合わせのコツ
プランニングをスムーズに進めるには、家族の意見をしっかりとまとめておくことが重要です。間取りや設備・デザインなどの希望は、できるだけ具体的にしておきます。家族それぞれの意見をまとめ、優先順位をつけておくと打ち合わせがスムーズに進みます。
打ち合わせの際は、疑問点をその場で確認しましょう。設備やインテリアの決定には時間がかかるため、カタログなどで事前に情報収集をしておくのがおすすめです。希望するプランが予算オーバーにならないよう、常にバランスを考えながら進めていきましょう。
住宅ローンの準備と手続き
住宅ローンの準備は、家づくりと並行して進める重要な要素です。まずは、住宅ローンの仮審査を受けることから始めます。仮審査で借入れ可能額が分かれば、具体的な予算計画が立てやすくなるのです。本審査は、工事請負契約を結んでから申し込みます。本審査には約1週間かかりますが、状況によっては1ヶ月程度必要な場合もあるため、余裕を持って審査するのがおすすめです。
土地を購入する場合は、つなぎ融資が必要になることもあります。住宅ローンの手続きは、スケジュールに大きく影響するため、金融機関との連絡を密にとり、遅れが出ないよう注意しましょう。
注文住宅の工期に関するよくある疑問

注文住宅の工期について、多くの方が気になる疑問にお答えします。
いつから準備を始めればいい?
注文住宅の準備は、住み始めたい時期の1年半から2年前から始めることをおすすめします。これは、土地探しから設計・建築工事まで、それぞれの工程に必要な時間を考慮した期間です。特に土地探しは時間がかかる工程のため、早めに始める必要があります。
また、住宅展示場の見学や資料請求などの情報収集も、時間をかけて行うことが大切です。住宅ローンの準備も同時に進める必要があるため、余裕を持って準備を始めましょう。早めに準備を始めることで、じっくりと検討する時間が確保でき、後悔の少ない家づくりが実現します。
工期を短縮することは可能?
注文住宅の工期を大幅に短縮することは難しいですが、いくつかの工夫で期間を少しでも短くすることは可能です。たとえば、建築工法の選択やプランニングの段階での素早い意思決定などが挙げられます。ただし、無理な工期短縮は品質に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
季節や天候による影響を考慮し、着工時期を工夫することで、工事がスムーズに進む場合もあります。短縮できる部分と、しっかりと時間をかけるべき部分を見極めることが大切です。建築工事自体の期間短縮には限界があるため、事前の準備をしっかりと行いましょう。
気をつけるべきトラブルは?
注文住宅の工期に影響を与えるトラブルとして、天候不順による工事の遅れや資材の調達の遅延などがあります。また、設計変更や追加工事が発生すると、工期が延びる原因となります。住宅ローンの審査が予定より遅れることもあるため、余裕を持った計画が必要です。
近隣との関係も重要で、工事に関する苦情があると作業時間が制限される場合もあります。こうしたトラブルを防ぐには、事前準備と関係者との密なコミュニケーションが欠かせません。予期せぬ事態に備えて、ある程度の余裕期間を設けておくことも大切です。
まとめ
注文住宅の完成までには、一般的に8ヶ月から15ヶ月の期間が必要です。土地探しからスタートする場合は、さらに3ヶ月から半年ほどの期間を見込む必要があります。建築工法や土地の状況・季節の影響なども工期に関係してくるため、余裕を持った計画が大切です。また、プランニングや住宅ローンの準備など、事前にしっかりと準備することで、スムーズな家づくりが実現できます。
株式会社デザインセンターオワリヤは1926年の創業以来、多くの方々の住まいづくりに携わってきました。店舗建築で培った確かな技術と設計力で、お客様の理想の住まいづくりをお手伝いいたします。注文住宅の計画から完成まで、経験豊富なスタッフが丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
家づくりを考え始めると、真っ先に浮かぶのが「どこに家を建てるか」という問題ではないでしょうか。
土地探しは、家づくりの土台となる大事なステップです。
今回は、これから土地探しを始める方向けに、流れや期間、押さえておくべきポイントを5つのテーマに分けてわかりやすく解説します。
これを読めば、土地探しの不安がきっと解消されるはずです
1. 土地探しの基本の流れ
2. 土地探しにかかる期間の目安
3. 土地探しの5つのポイント
4. 失敗しないためのチェックリスト
5. 土地探しのプロに相談するメリット
1. 土地探しの基本の流れ
土地探しは、闇雲に不動産サイトを眺めるだけでは中々進みません。
計画的に進めることで、理想の土地を見つけやすくなると思います。
1. 希望条件の整理
家族の希望やライフスタイルをもとに、「エリア」「予算」「広さ」「周辺環境」などを明確にします。
ここがブレていると、選択肢が多すぎて迷いが生じてしまいます。
2. 情報収集
不動産会社のサイトをチェックしたり、住宅展示場や建築会社の土地情報も活用しましょう。
3. 見学・現地確認
実際に現地を訪れて、日当たり、風通し、周辺の環境を確認します。
地図や写真ではわからない“リアルな体感”が重要です。
2. 土地探しにかかる期間の目安
「土地探しにはどれくらい時間がかかるの?」と不安に思う人も多いのではないでしょうか。
平均的なスケジュールは以下の通りです。
- 情報収集・見学:2〜6か月
- 契約・決済:1〜2か月
早い人では1か月程度で見つかることもありますが、1年以上かかるケースも少なくありません。
半田市でも成岩地区や乙川地区や駅からの利便性のあるエリアは人気で、中々良い土地情報は出にくいので、情報はすぐチェックすることが重要です。
3. 土地探しの4つのポイント
1. エリアの決定
エリアは、家族の生活に大きな影響を与えます。
実際に住むことを考慮して、職場や学校までの距離、商業施設の有無、交通の便などに優先順位をつけて決めていきましょう。
2. 土地の形状と広さ
理想の家を建てるには、土地の形が意外と重要です。
整形地(四角形)であれば、建物のプランが立てやすいですが、金額は高めな傾向にあります。
変形地は工夫が必要ですが、施工会社と土地探しをする場合は良い提案を受けれるかもしれません。
3. 日当たり・風通し
家の快適さに直結するのが、日当たりと風通しです。
現地を訪れて、朝・昼・夕方の様子を確認するのがポイントです。
4. 価格のバランス
土地代が高すぎると、家の建築費にかけられる予算が減ります。
資金計画を立て予算配分のバランスを考えつつ、トータルでの家づくりの費用感を見ておきましょう。
4. 失敗しないためのチェックリスト
土地選びに失敗しないためのチェックポイントをまとめました。
これを押さえておけば、後悔のない土地選びができますよ。
1.見えないコストを見逃さない
土地代だけでなく、造成費用、解体費用、上下水道の整備費なども見積もりに入れておきましょう。
2.現地を複数回訪れる
平日と休日、昼と夜の様子は異なります。現地見学は複数回行うのがおすすめです。
3.不動産会社の信頼性
不動産会社選びも大切です。口コミや評判をチェックし、親身になって相談に乗ってくれる会社を選びましょう。
4.土地の制限に注意
建ぺい率や容積率、建築協定など、建てられる建物の大きさが決まっている場合があります。
5. 土地探しのプロに相談するメリット
最後に、土地探しをスムーズに進めるための“裏ワザ”をお伝えします。
それは、建築会社に相談することです。
建築会社は、家を建てるプロなので、「この土地だと家が建てやすい」「この土地はコストがかかる」など、専門的なアドバイスがもらえます。
不動産会社では教えてもらえない、家づくり目線のアドバイスが得られるのは大きなメリットです。
さらに、建築会社は独自のネットワークで土地情報を持っていることも多いので、未公開の土地情報を紹介してもらえるチャンスもあるかもしれません。
まとめ
土地探しは、家づくりのスタートラインです。
計画的に進めることで、後悔のない家づくりが実現します。
希望条件の明確化、情報収集、現地見学、契約の流れをしっかり理解し、エリアや形状、価格のバランスを考えながら進めましょう。
自力で探すのも良いですが、建築会社のサポートを受けるのも1つの方法です。
家づくりのプロに相談しながら進めれば、安心感が格段に増しますので、ぜひこの記事を参考にして、理想の家づくりを実現してください!
注文住宅を建てるためには、まず土地を探すことから始まります。しかし、土地選びは簡単ではありません。土地は一度購入すると変更が難しく、その後の暮らしに大きな影響を与えます。この記事では、注文住宅の土地探しに必要な基礎知識と理想の土地を見つけるためのポイントについて解説します。
注文住宅の土地探しを始める前に準備すること
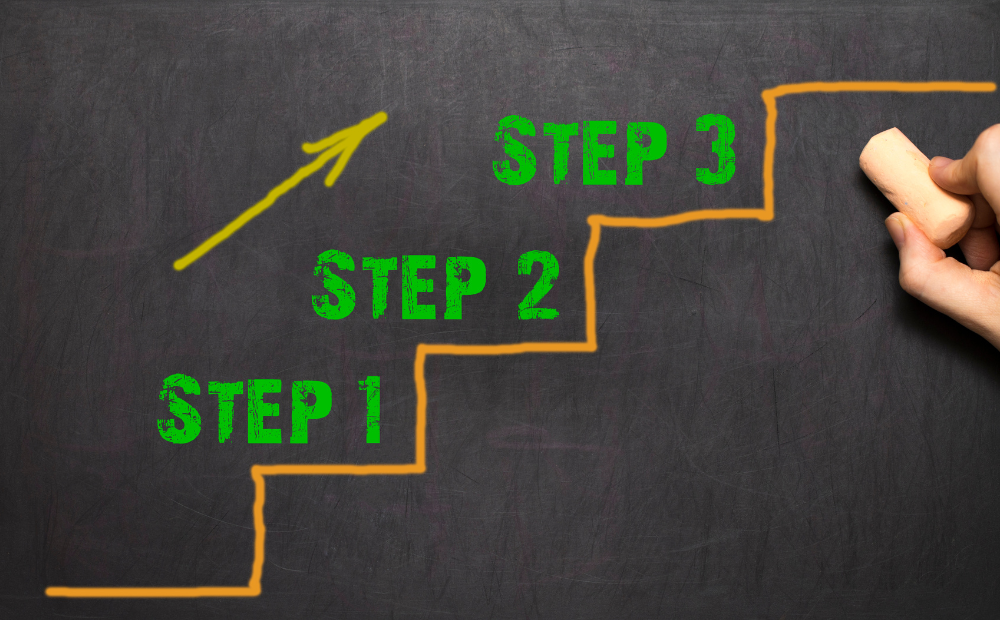
土地探しを始める前にしっかりとした準備が必要です。ここでは、予算の考え方から実際の土地探しにかかる期間、希望条件の決め方まで、準備段階で押さえておきたいポイントについて説明します。
予算配分の考え方
注文住宅を建てる際の予算は、土地代と建物代に大きく分かれます。予算を考える際は、土地代だけでなく、建物を建てるための費用も必ず確保しておく必要があります。土地購入時には諸費用も発生します。
登記費用・不動産仲介手数料・地盤調査費用・税金なども計算に入れておきましょう。土地購入時には手付金が必要となることが多く、まとまった自己資金の準備が重要です。
土地探しの期間の目安
土地探しにかかる期間は、通常3か月から1年程度です。理想の条件に合う土地がすぐに見つかることは少ないため、余裕を持って探し始めることが大切です。条件の良い土地は人気が高く、すぐに売約済みになることも珍しくありません。
土地が見つかってから実際に購入するまでには、現地調査や契約手続きなどにも時間が必要です。住宅ローンの審査期間も考慮に入れましょう。焦って判断を誤らないよう、時間的な余裕を持って土地探しを始めることをおすすめします。
希望条件の優先順位付け方
土地選びの希望条件は、必ず優先順位をつけましょう。最寄り駅からの距離・土地の広さ・日当たり・学区・買い物のしやすさなど、さまざまな条件があります。すべての条件を満たす土地を見つけることは難しいため、どの条件を重視するかをあらかじめ決めておくことが重要です。
将来の家族構成の変化も考慮に入れましょう。子育て世代であれば、学校や公園までの距離を重視するかもしれません。共働き世帯なら通勤時間や利便性が重要になるでしょう。優先順位は家族で話し合って決めることをおすすめします。
土地探しの5つの方法とメリット・デメリット

土地を探す方法はいくつかあります。それぞれの方法には特徴があり、組み合わせて利用することで理想の土地が見つかりやすくなるでしょう。ここでは、代表的な5つの探し方について説明します。
不動産会社に依頼して探す
不動産会社に依頼する方法は、最も一般的な土地の探し方です。不動産会社は土地の専門家として、その地域の相場や特徴を熟知しています。物件情報も豊富で、まだ一般に公開されていない土地の情報を持っていることもあります。ただし、その不動産会社が扱っている物件しか紹介されない場合もあることは覚えておきましょう。
ハウスメーカーと一緒に探す
住宅を建てることが決まっている場合は、ハウスメーカーと一緒に土地を探すのも良い方法です。ハウスメーカーは建築のプロとして、その土地に建てられる建物の制限や日当たり、地盤の状態など、家づくりの観点から土地を評価してくれます。
土地と建物の予算配分も、具体的なプランが立てやすくなるでしょう。また、ハウスメーカーによっては独自の土地情報を持っていることもあります。建築条件付き土地の場合は、指定されたハウスメーカーでしか建物を建てられないため、注意が必要です。
インターネットで探す
不動産情報サイトで土地を探す方法は、手軽に始められる探し方です。パソコンやスマートフォンからいつでも物件情報を確認でき、価格や面積、駅からの距離など、条件を細かく指定して検索できます。
地図情報と連動しているサイトでは、周辺の施設や環境も確認しやすいでしょう。航空写真で土地の形や周辺の様子を見ることもできます。ただし、インターネットの情報は更新が遅れていることがあり、既に売約済みの場合もあります。
現地を歩いて探す
希望するエリアを実際に歩いて土地を探す方法は、その地域の雰囲気を直接感じられる大きな利点があります。住宅地の様子や、近隣住民の雰囲気、周辺の施設など、実際に足を運ばなければ分からない情報を確認できるのが特徴です。
朝夕の通勤・通学時の様子や夜間の明るさ、休日の過ごし方などについても、自分の目で確認することが可能です。売地の看板を見て、その場で不動産会社に問い合わせる手段も取れます。
インターネットにはまだ掲載されていない土地を見つけられる可能性もあります。ただし、時間と労力がかかり、効率は良くないため、ある程度エリアを絞り込んでおくのがいいでしょう。
銀行に相談して探す
銀行には、担保物件の売却情報など、独自の土地情報が集まっています。住宅ローンの相談と合わせて、土地探しの相談をすることが可能です。銀行は土地の資産価値を評価する専門的な知識を持っています。
また、住宅ローンの事前審査を受けることで、予算の目安を具体的に把握できます。土地が見つかってから住宅ローンの相談をするのではなく、土地探しの段階から融資の可能性を確認できるのが利点です。ただし、銀行で紹介される物件数は限られており、土地探しの補助的な手段として考えるのがいいでしょう。
注文住宅の土地選びで必ずチェックすべき6項目

土地を選ぶ際には、多くの確認項目があります。一度購入した土地は変更が難しく、将来の暮らしに大きな影響を与えます。ここでは、土地選びで特に重要な6項目について詳しく解説していきます。
周辺環境と生活利便性
周辺環境は日々の暮らしを左右する重要な要素です。スーパーマーケットやコンビニエンスストア、病院、郵便局、銀行などの生活利便施設までの距離を確認しましょう。子育て世帯であれば、保育園や学校、公園までの距離も大切な判断材料になります。
通勤・通学の利便性も重要です。駅やバス停までの距離、主要道路へのアクセスなども確認が必要です。現地に足を運び、平日や休日、朝夕など、異なる時間帯で周辺の様子を確認することをおすすめします。
土地の形状と向き
土地の形状は、建てられる建物の設計に大きく影響します。整形地は比較的自由な建物プランが立てやすく、スペースも有効活用しやすいです。一方、不整形地や旗竿地は、建物の配置や間取りに工夫が必要になります。
土地の向きは日当たりに関係します。南向きの土地は一般的に日当たりが良好ですが、土地の形状や周辺建物との関係で、必ずしも南向きが最適とは限りません。東向きは朝日が入り、西向きは夕方まで日が差します。
北向きは日当たりに課題がありますが、プランの工夫で快適な住まいを実現できます。専門家に相談しながら、土地の特性を活かした建物プランを検討することが大切です。
道路との関係性と接道状況
土地と道路の関係は、建築基準法で細かく規定されています。建物を建てるためには、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが必要です。
道路の幅が4メートル未満の場合は、セットバックが必要になり、実際に使える土地の面積が減少します。道路が私道の場合は、通行権や維持管理の取り決めを確認する必要があります。
地盤の状態と高低差
地盤は住宅の安全性に直結する重要な要素です。軟弱地盤の場合は、地盤改良工事が必要になり、建築費用が増加する可能性があります。土地の履歴も重要で、かつて池や沼地だった場所や、埋立地は地盤が弱い傾向にあります。
また、土地の高低差も確認が必要です。急な斜面がある場合は、擁壁工事が必要になることがあります。土地が低い場合は、雨水の排水や浸水対策を考える必要があります。地盤調査は専門家に依頼し、必要な対策工事の内容と費用を事前に把握することが重要です。
日当たりと通風
日当たりと通風は住まいの快適性を大きく左右します。土地の日当たりを確認する際は、季節による太陽の高さの変化も考慮する必要があります。夏至と冬至では日影の位置が大きく異なります。
周辺に高い建物がある場合は、その建物による日影の影響も確認しましょう。通風に関しては、主風向や周辺建物との位置関係が重要です。良好な通風は、夏の暑さ対策や室内の換気に役立ちます。特に日本の夏は蒸し暑いため、風通しの良さは重要なポイントとなります。
法的な建築制限
土地には様々な法的制限が設けられています。用途地域による建築制限、建ぺい率、容積率などの基準を確認することが重要です。用途地域によって建設できる建物の種類や規模が制限されます。
建ぺい率は建物の建築面積の上限を定め、容積率は延べ床面積の上限を規定。高さ制限や斜線制限なども、建物の設計に影響を与えます。これらの制限は地域によって異なるため、市区町村の都市計画課などで正確な情報を確認することが大切です。
まとめ
注文住宅の土地探しは、将来の暮らしを左右する重要な決断です。土地購入前には、予算配分から法的制限まで、さまざまな要素を慎重に検討する必要があります。また、土地探しの方法も複数の手段を組み合わせることで、より良い物件に出会える可能性が高まります。
土地の条件は、立地や環境、地盤など多岐にわたるものです。すべての条件を完璧に満たす土地を見つけることは難しいため、優先順位をつけて検討することが大切です。
株式会社デザインセンターオワリヤでは、50年以上にわたり培ってきた店舗建築の経験と技術を活かし、土地探しから住宅建築まで一貫してサポートいたします。土地の特性を活かした建物プランのご提案や土地選びのご相談も承っております。理想の住まいづくりに向けて、どうぞお気軽にご相談ください。

 時間の森(ときのもり)
時間の森(ときのもり)
